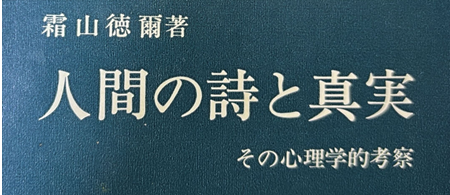弁護士のブログBlog
「最高裁判所誤判事件」は、山梨県北都留郡巌村(現:上野原市)で起きた強盗致死事件をめぐって起きた。東京高裁が、旧刑訴法で審理を行い、1949年3月1日に無期懲役判決を言い渡したのに対して、大西幸高弁護士が「東京高裁は1948年12月18日に第2回公判以来、翌1949年2月15日まで開廷しなかった。これは『15日以上開廷しなかったら公判手続を更新すべし』という旧刑訴法353条に違反している」という理由で上告したところ、最高裁判所第二小法廷(裁判長:霜山精一判事)は、弁護側の上告を全面的に認めた上で、原判決を破棄して東京高裁に差し戻した。
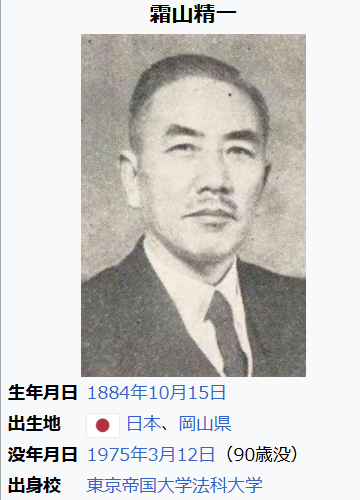
ところが、新刑訴法と同じく1949年1月1日から施行されていた、刑事訴訟規則施行規則第3条第3項によれば、「開廷後引き続き15日以上開廷しなかった場合においても、必要と認める場合に限り、公判を更新すれば足りる」と規定されていたことから、実は、上記東京高判は適法で、上記最高裁判決は、「上告棄却」をすべきだった(つまり、「破棄差戻し」は誤判だった)ということになる。
その後、同年10月17日、最高裁・裁判官会議での協議の結果、三淵忠彦最高裁長官は、誤判をした最高裁第二小法廷の各判事に対し、辞職勧告をし、その旨をマスコミに公表したが、霜山判事らは、「裁判官の責任はあくまで憲法ならびに法律に従って決められるべきである」として辞職を拒否した。
これに対し、国会の裁判官訴追委員会は、同年12月20日、「…その程度をもって直ちに『著しく』又は『甚しく』の重さに相当するものとは決し難い」として不訴追を決定したが、最高裁長官が三淵判事から田中耕太郎判事に替わった後、1950年6月24日、裁判官分限法による分限裁判(最高裁大法廷昭和25年6月24日決定)で「最高裁判事として職務の遂行に注意を欠き、裁判所法第49条の職務上の義務に違反した」として、裁判官分限法第2条が適用され、霜山判事ら4名の裁判官は、過料1万円の処分を受けたらしい(ウィキペディア)。
霜山清一・最高裁判事の前職は、大審院長であり、初代最高裁長官になっていれば、誤判事件に遭わなくて済んだであろうに…。
むかし学生時代に読んだ、霜山徳爾先生(上智大学教授;臨床心理学)の「人間の詩と真実」(中公新書)を読み返して、感銘を受けた後、同先生の御経歴をウィキペディアで調べたら、御父様が、高名な法律家(元大審院長、最高裁判事)であられたことを知って、さらなる感銘を受けた次第。