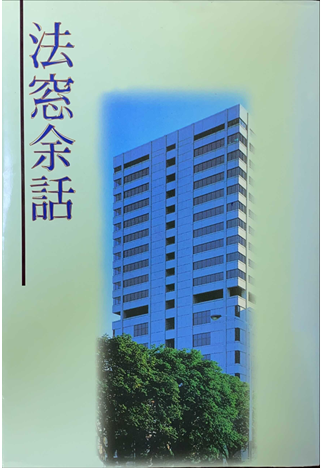弁護士のブログBlog
裁判官も、弁護士の多くも、通常、数十件の事件を同時並行して手掛けている。
弁護士の場合、受任事件の全てが訴訟事案(裁判)というわけではないため(調査事案や、契約書のチェック、示談交渉等もある。)、通常、裁判官の手持ち事件数ほどの数の事件を常時もっているわけではない。しかしながら、受任事件が裁判事案となると、1ヶ月~1月半毎に裁判期日がめぐってくるところ、その間に、事案の詳細を忘れてしまうことが日常的に起こる。
このため、受任事件ごとに簡明な手控えメモ(備忘録)を作成しておくことは、医師が必要不可欠・最小限の診療情報をカルテに記録するのと同様、弁護士にとっても、必要不可欠の職業技術である(裁判手続に係る進行メモについては、最近は、関係者間で認識を共通にするため、主任裁判官の方で作成してくれる例もあり、それを控えておくことで足りる場合も少なくないが、訴訟記録、特にどの証拠がどのような重要な意味を持つのかという微妙な問題や、時にいいアイデアが浮かんでも、直ちにメモに残しておかないと忘れてしまう。たとえ、準備書面に書いておいたはずのことであっても、どの書面の何処に書いておいたかをメモしておかないと記載箇所を探すのに時間を浪費してしまうことになる。)。
そこで、有能な裁判官は、一体、どのような手控えメモを作成されているのか?、という問題はかねてから、手控えメモの作成が苦手な私のような弁護士にとっては重要な関心事である。昔、倉田卓次判事(高名な東京高裁判事)が、手控えメモの作成方法を法律雑誌にて紹介されていたが、法律用語を独自の記号に置き換える独自の手法は、マネできるものではなかったし、私にとっては必ずしも参考になるものではなかった(記号の意味自体を忘れてしまうこともあり得る。)。また、30年以上も昔、民事裁判の実務修習のとき、大分地裁民事部のH部長(後の京都大学法科大学院教授)の手控えメモを見せていただいただいたこともある。しかしながら、やはり、あんな綺麗な手書き文字で、重要事項だけを要領よく拾い出すという技術は、その前提として、事件の筋を見極める眼力が磨かれている必要があり、よほど裁判に習熟しないとマネできるものではないと思った記憶がある。
さて、ここ一ヶ月内のブログで、「布川事件」の再審開始決定(東京高裁・即時抗告審)を決定づけた、高名な裁判官として、門野博元判事のことに言及してきた。
私自身は、刑事弁護人として、同元判事から直接判決を受けたことはないが、上記「布川事件」決定書のみならず、同判事が著述された各種論文・論稿から学んだことは少なくない。だが、実は、「布川事件」の再審開始に係る決定書に記述されている論証構造(刑事訴訟記録における証拠の読み込み方)に次いで、私が門野元判事から最も学んだことは、実は、手控えメモ(備忘録)の作り方である。
門野元判事自身、「野口悠紀雄『続「超」整理法・時間編―タイム・マネジメントの新技法』(中公新書)」の受け売りであることを述べられておられるが、同元判事が書かれているエッセイ「超整理法」の中に、次のような記述がある。
「仕事を中断したときに生ずる物忘れや資料紛失などによる能率の低下の諸症状」のことを「中断シンドローム」という。
「明日の自分は赤の『他人』と考えて、多少苦しくてもその他人が理解できるまでは仕事をしておく、できれば八割くらいは仕上げておく」
「明日の自分は『他人』と考えてできるだけ分かりやすく、丁寧に伝達事項を残しておけば、前の思考が無駄になってしまうということもありません(手控えの重要性もここにあるのでしょう。)」と(『法窓余話』(財)司法協会より)。
この関係で、私は、私自身のため、「明日は赤の『他人』にして、できの悪い中学生でも」解るようにメモを残すようにしている。
そして、日誌として記録・記憶しておきたいことは、なるべくブログに書き残すようにしている。
ちなみに、門野元判事の著名な論稿として、「証拠開示に関する最近の最高裁判例と今後の課題―デュープロセスの観点から」(原田國男判事退官記念論文集159頁以下)、「裁判員裁判への架け橋 刑事裁判ノート」(判例タイムズ社)がある。刑事裁判に携わる者として必読文献であろう。