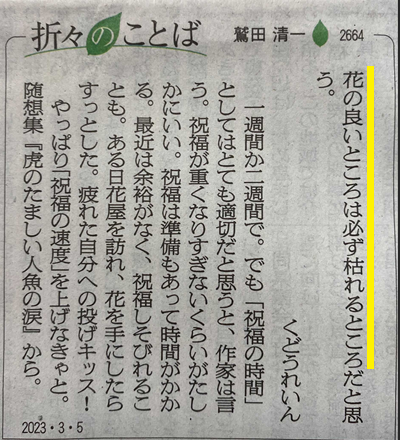弁護士のブログBlog
古今和歌集で勅撰されし「桜の花」の和歌
- 2023-03-06
古今和歌集・巻第二 春歌下の殆どが「桜」が歌題になっており、かつ、その多くが、桜花があっけなく散っていくのを惜しむ歌である。
●世の中に たえて桜の なかりせば
春の心は のどけからまし
(在原業平朝臣)
[現代語訳]世の中に、桜というものがまったくなかったなら、春はどんなにかのどかな気分でいられるだろうに。
●ことならば 咲かずやあらぬ 桜花
見るわれさへに しづ心なし
(紀貫之)
[現代語訳]どうせ散ってしまうものなら、いっそ咲かずにいてくれた方がよいのに。桜が散るのはあわただしいものだが、見ている自分まで、落ち着いた気分でいられないから。
●ひさかたの 光のどけき 春の日に
しず心なく 花の散るらん
(紀友則)
[現代語訳]日の光がのどかに輝いてい春の日に、なぜ、あわただしく花は散るのであろうか。
だが、昔から、「散る」ことを、逆に、喜ぶ向きもある。老荘思想のように。
●残りなく 散るぞめでたき 桜花
ありて世の中 果(は)ての憂(う)ければ
(よみ人しらず)
[現代語訳]盛りがすむと、未練げもなく散ってしまう、それが桜のいいところだ。世の中の常として、いつまでも永らえていると、ろくなことにならないものだから。
以上、「新潮日本古典集成・古今和歌集」(奥村恆哉校注)
昨日の「折々のことば」も、昔ながらの言葉ですな。